問屋町
今日の一日
2026.02.07

TITLE
コラム
2025.02.20
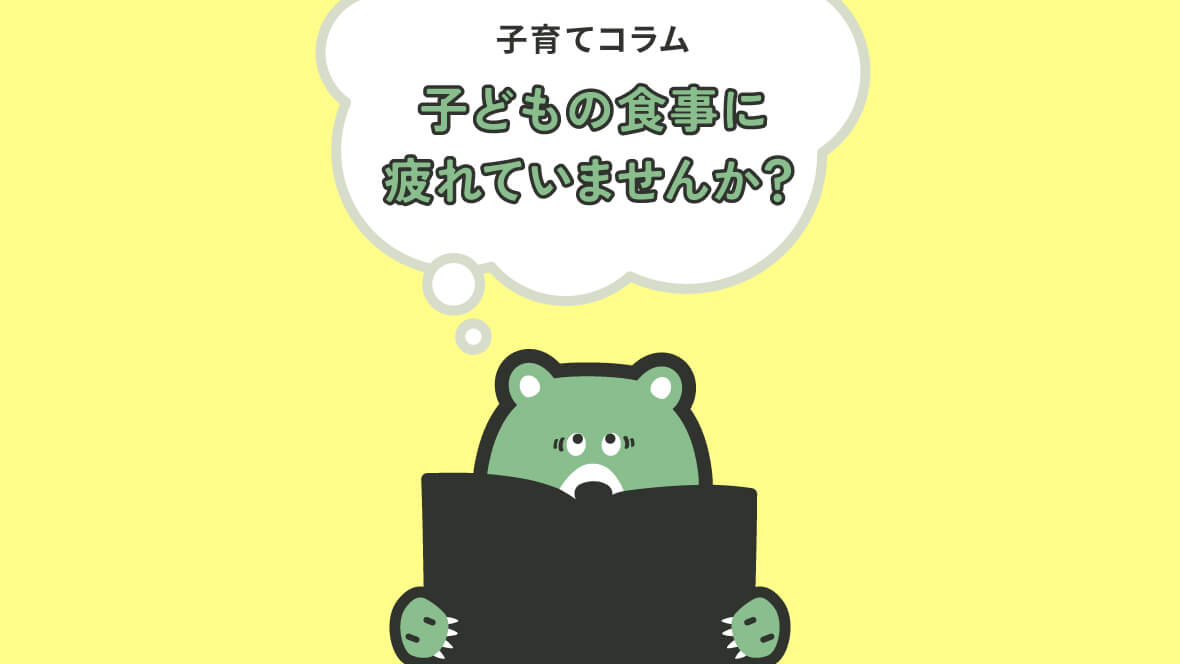
乳幼児期に食が大切であるのは、栄養補給だけでなく、心身の発達や生活習慣の基礎を育むためです。
栄養補給
心身の発達
生活習慣の基礎
乳幼児期の食育では、子どもが楽しく食べられる環境づくりが大切です。

とは言え、毎日の育児・家事・仕事に追われ、子どもが思うように食べてくれなかったり、疲れて食事を作ることが面倒だと感じることもあると思います。
好き嫌いがある時期
子どもが喜んでくれると思って頑張って作っても食べてくれないと、ガッガリすることもあるでしょう。期待しすぎると辛くなってしまうこともあります。
子どもに好き嫌いがある時期は、残すことが当然と思って気持ちを楽にしましょう。
1度は口に入れて食べようとしたのにすぐに出してしまうと「嫌いなのかな?」と思ってしまいますが、食べづらかったり、味や香りに慣れていないことが原因ということもあるようです。
子どもが食べやすい調理方法、味付けなどにすることで食べるようになることもあります。
乳歯が生え揃わないと大人と同じように簡単に食材をかみ切ることができません。子どもの歯の生え方をチェックして、子どもが食べやすい切り方や形になるように工夫しましょう。
野菜と肉や魚では、加熱による変化の仕方が違うので注意しましょう。
野菜は加熱するほど柔らかくなりますが、肉や魚はかたくなってパサパサになるので加熱時間を加減しましょう。
栄養バランスが気になる
成長の過程の中で好き嫌いが出てくる時があります。
今は、「○○が好き!」「⚫️⚫️が嫌い!」と言っていてもしばらくすると別のものになっているかもしれません。
このような食べムラは、2歳頃に多く見られ3〜4歳頃になると落ち着いてきます。
栄養のバランスは、1日単位ではなく、1週間単位で見てそれなりに食べていれば大丈夫だと考えられるといいですね。
周りの大人が食べて見せることも大切になってきます。

お惣菜や冷凍食品を使って手抜きすることに罪悪感がある
食事を準備する以外にも、洗濯や掃除、子どもの世話など毎日やることは次々とたくさんあると思います。
視点を少し変えてみましょう。
お惣菜や冷凍食品を使うことを「手抜き」と考えるのではなく、「上手に利用している」と考えるのです。
臨機応変に賢く利用しているんだと見方を変えることで気持ちが楽になりますよ。
とはいえ、子どもは濃い味の食べ物に慣れてしまうと、どんどん濃い味が好きになってしまいます。1〜2歳の子どもが1日に摂取して良い塩分量は、成人女性の半分程度です。
使用する時には、食品表示を確認するなどして気をつけていきたいですね。
周りの方や便利なサービスにも頼りながら、過ごしていきましょう!
ご質問や聞きたいことなどありましたら、スタッフにお声かけください。